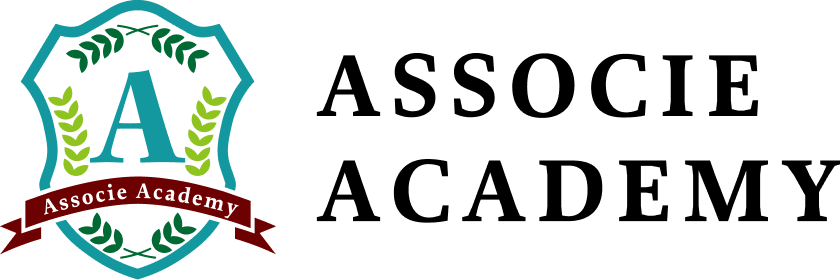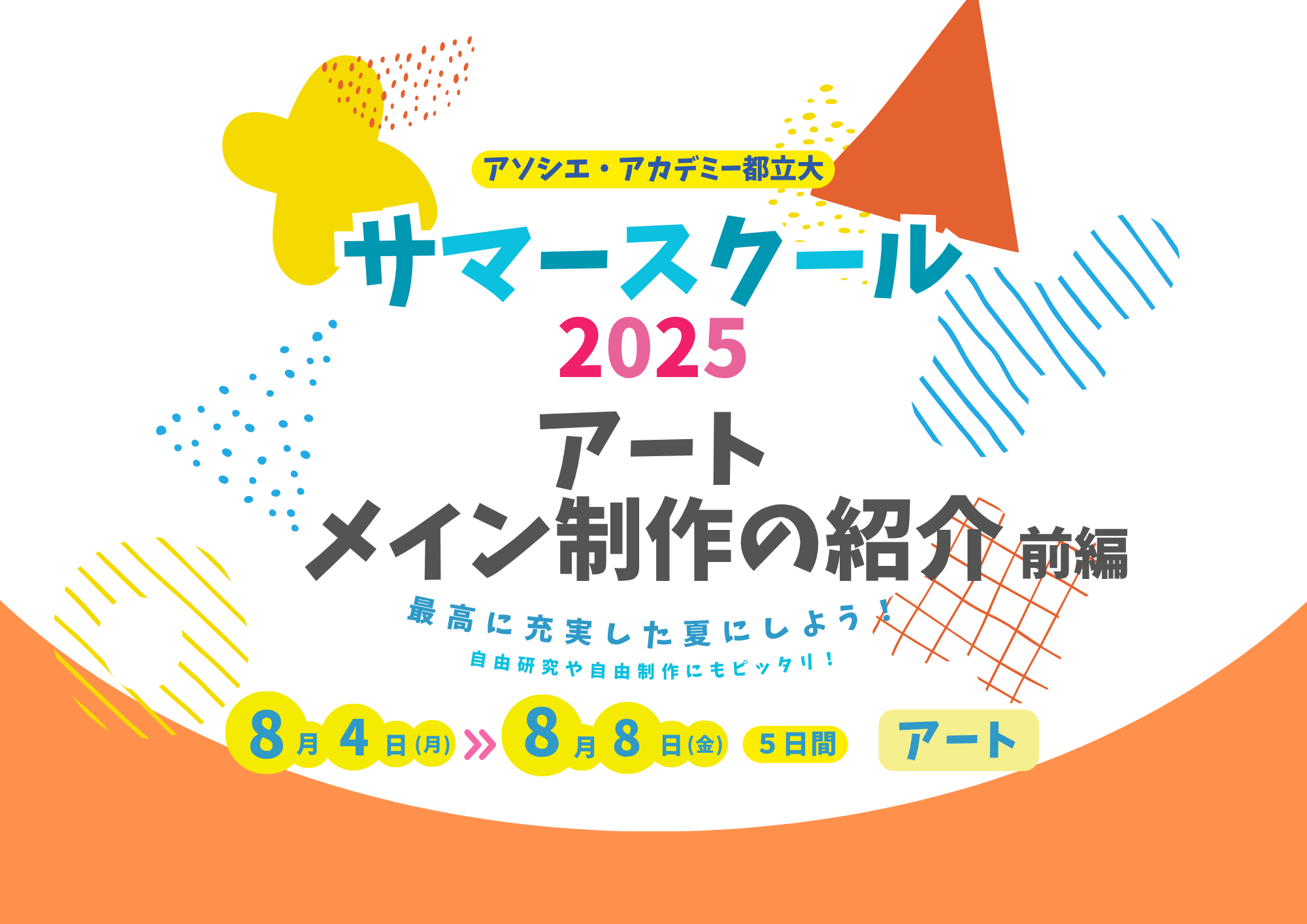ドッジボールで成長しよう
スポーツ
カリキュラム
2025.09.05

小学生スポーツ総合クラス
アソシエ・アカデミー都立大の小学生スポーツ総合クラスは、様々なスポーツゲームに取り組みます。
その中でも、子どもたちはドッジボールが大好きです。
もちろん、そうでない子もいますが、色々な遊び方や種類があることも知ってもらいたいと思っています。
小学生のスポーツクラスで行うドッジボールは、ボールを複数使うルールで行うことが多いです。最近行っているのは、部屋を半分に分けてチームごとに投げ合うシンプルなゲーム。当たれば座る。仲間がキャッチすれば復活する。どちらが最後まで多く残っていられるかといったゲームです。

通常のドッジボールはボールを1個使って行うゲームですが、ボールが複数あることで「今どっちに何個ボールがあるかな」といった状況判断が生まれます。そして「当てたいけど、当てられたらどうしよう」といった心理的な状況も子どもたちには生まれます。
最初は、この2つのポイントを大切にして練習していきます。
ボールを持った子はまず状況判断をします。例えば、3つのボールを使ってドッジボールを行っていたら、ボールを持った子は「今は3つとも自分たちのチームにあるから、安心して当てにいけるぞ」「他の2個は相手チームが持っているな、どうしよう」などと考えだします。
「当てたいけど、遠くからだと当たらないし、前に行けば当てられちゃうかもしれない!?」
そう考えているうちに、中途半端な位置からボールを投げてしまって「ボールは避けられたけど、結局相手には届かなかった」といった状況が繰り返されてしまいます。
「上手になるには何が大切だと思う?」
「当たってもいいから、積極的に」
「当たったら、潔く応援」
「失敗の仕方(当たり方)を工夫しよう」
レッスン中はこれらの言葉を何度も伝えます。子どもたちからすれば「当てられた」ことは当然「失敗」と思ってしまいますが、次にもう一度チャレンジしたときに「上手くいくかもしれない」といったヒントが得られるなら、それは良い事だと考えられるようになってほしいです。そうすれば、失敗も長く引きずらないで次に向かうことができます。

幼児期や小学生年代では、「投げる」「捕る」といった技術が足りていないからこそ、スポーツゲームを通して、良い考え方が身につくような習慣も作れたらと思っています。
もちろん技術も練習を重ねる中で伸びていきますので、これから身体が大きくなって、技術もさらに伸びてきたときに、考え方も良くなっている子はスポーツをもっと楽しむことができるはずです。
「うまく失敗して、うまく立ち直る」
これが大切ではないかな。
良い考え方ができれば、みんなスポーツや運動がさらに上達していくと思います。